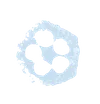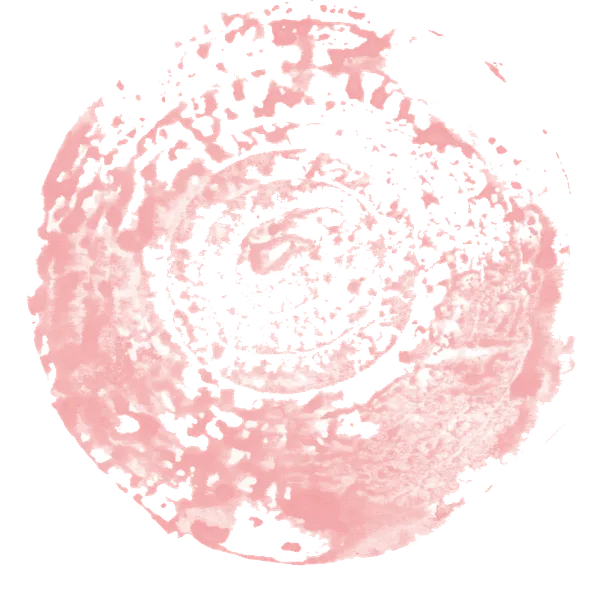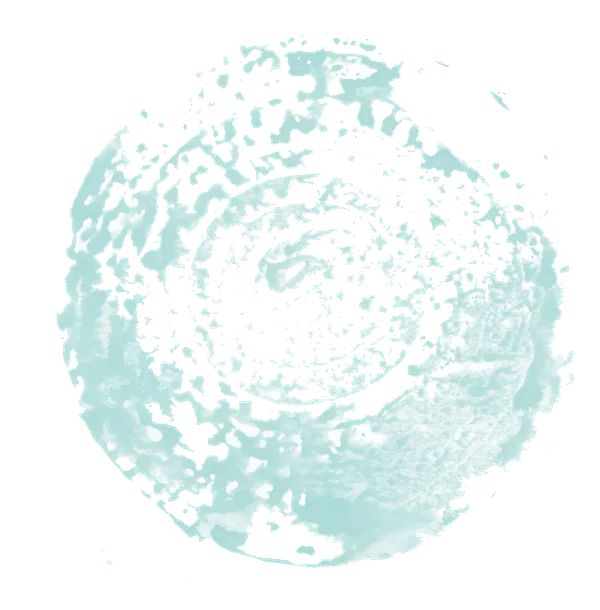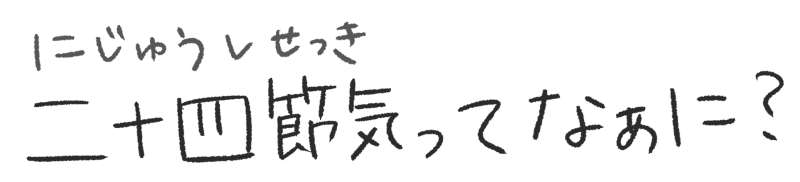
わたしたちが住んでいる日本には、春夏秋冬という美しい四季があります。
気温だけでなく、季節ごとに育つ野菜や咲く花、活発になる生き物が異なり、季節にちなんだ日本ならではの行事もたくさんあります。
二十四節気は一年を春夏秋冬の4つに分け、それぞれをさらに6つに分けた、約半月ごとに移り変わる季節の指標です。
細かな季節の変化を表しているため、常に天候に左右される農業の目安として重宝されました。


2月4日ごろ
暦の上ではもう春です。旧暦では一年の始まりでもあります。
2月の節分は、立春の前日。つまりは季節の節目でもあり、一年の節目。冬と春の季節の変わり目は邪気が入りやすいと言われていることから、鬼を払う風習がうまれたそう。
体感としてはまだまだ寒いけど、少しずつ春のはじまりを感じることが増えていく時期。
冬至以降、少しずつ日が長くなってきていることもそのひとつです。
これまで降っていた雪が雨に変わり、氷が溶けて雪解けの時期となります。雪解けの水は田畑を潤し、農耕の準備を始める目安とされてきました。
北のほうではまだ寒さは続きますが、少しずつ春の日差しを感じる日が増えていき、春一番が吹くのもこのころです。
このころには梅が見ごろを迎えます。もともと「花見」といえば梅を鑑賞していたほど、日本人に愛されている花です。

2月19日ごろ

3月5日ごろ
春の陽気に誘われて冬ごもりしていた虫たちが動き出す頃。
土を覆っていた雪がとけて、土自体に日があたるようになり、巣の中も暖かくなります。すると春を感じた虫や冬眠していたいきものが目覚め始めます。
3月から4月は雨の多い時期でもあります。
このことを「菜種梅雨」とも呼び、菜の花をはじめさまざまな花を咲かせる雨とされます。
二十四節気をさらに細かくした七十二候では「桃はじめて笑う」の時期。昔は花が咲くことを「笑う」と言っていました。
昼と夜が同じ長さになった日、春分。
太陽が真東から昇り、真西に沈んでいく日です。
春分は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。
この時期を目安に農作業を本格的に始めることが多いそう。
また、春分の日は「お彼岸」の中心日。
ご先祖様への感謝のきもちも込めて、お墓参りや供養を行うならわしがあります。
春分の日はこれらの意味で特別な一日と捉えられていることがわかります。

3月21日ごろ

4月5日ごろ
「すべてのものが明るく清らかで生き生きしている」という意味です。
清明のころには「清明風」と呼ばれる風が吹きます。南東から吹く心地の良い風のことで、冬の終わりと春の訪れを知らせてくれます。
このころに降る雨は「発火雨」「桃花雨」「杏花雨」とも呼ばれます。やわらかく静かに降る雨で、桃の花に降る雨が火を発しているように見えることからそう呼ばれることになったとのこと。
花が咲き、柔らかな風にのって燕を見かけるようになります。
穀雨は恵みの雨が地面に降り注ぎ、田畑を潤す時期。
田植えを準備する目安としてとらえられてきました。
寒さを感じることは少なくなり、過ごしやすい日が多くなります。
穀雨の終わりごろには「八十八夜」がやってきます。立春から数えて88日目にあたる日のことで、「茶摘み」の歌にもあるように新茶の時期です。

4月20日ごろ


5月6日ごろ
陽気に包まれ、夏の気配を感じる頃。新緑に心地よい風が吹いて、一年の中でも過ごしやすくさわやかな季節です。
この時期の行事といえば「端午の節句」。菖蒲を使った邪気払いの行事が由来となっています。菖蒲を「尚武」「勝負」とかけて、男の子の健やかな成長を願う日とされてきました。菖蒲をお風呂に入れて楽しむのもそのためです。
子どもの日に食べる柏餅は、実は日本独自のもの。柏の葉は新芽が育つまで古い葉が落ちないため、子孫繁栄の想いを込めた縁起物として食べられています。
日の光がますます強まり、若葉は深みを増し、草花をはじめあらゆる命が満ちていく季節です。麦の穂が育ち収穫を迎えます。そのため、「ほっと一安心=ちいさな満足=小満」とも。麦の収穫に加え、蚕は育ち盛り、そして田植えもますます盛んに。農家は大忙しの時期です。
このころには「走り梅雨」が見られます。本格的な梅雨を前に数日間ぐずつく空模様のことです。明けて陽気が見られた後、本格的な梅雨を迎えます。

5月21日ごろ

6月6日ごろ
稲や麦のような穂がある植物の種をまく時期であることから芒種と言われます。現在の田植えはもう少し前に始まりますが、昔はこの頃だったそう。全国で豊作を祈るお祭りが行われます。
日本では「6歳の6月6日に稽古を始めると上達する」とされています。片手で指をおって順に数を数えると、6で小指をたてる形になり、小指のたつ様子を「子を立てる」と捉え、そのように言われるようになりました。
少しずつ雨空が多くなり梅雨を迎えます。梅雨は「梅が熟す頃の雨」であることからそう呼ばれるようになりました。
一年で一番昼が長く、夜が短くなる日として知られています。そのことから、太陽の力が一年でもっとも強まる日とされ、世界各地でお祭りや行事が催されます。
梅雨の真っ只中、恵みの雨を受けて稲はすくすく成長していきます。
雨の日に濡れながら咲く姿が美しい紫陽花は、実は日本原産だそうです。このように雨の中で美しく咲く花を「雨降花」と呼び、親しまれてきました。ツリガネソウやすみれなど、全国的にいくつもあり、その言い伝えも「摘むと雨が降る」「咲くと雨が降る」だったり地方によってさまざまだそうです。

6月21日ごろ

7月7日ごろ
ここから次の暦「大暑」までの期間を暑中といいます。とはいえ暑中見舞いの時期は諸説あり…正式には大暑から立秋までなど、様々なようです。
この頃になると梅雨明けの兆しが見られます。
蓮の花が咲き始めるのもこの頃。
早朝に咲き、昼頃には閉じてしまうのでなかなか美しく咲く姿を見るのは難しいですが…見られたら爽やかな気持ちになれますね。
「おおいにあつい」時期ですが、暑さのピークはもう少しあと。
現代ほどではないにせよ、昔ももちろんこの時期は暑かったそう。
昔の人々は、軒先に風鈴、強い日差しにはよしずを掛け、夜は川に船を浮かべて風にあたるなど、様々な工夫で涼を感じていました。
動物園の動物たちに氷をプレゼントする「打ち水」イベントも、「大暑」の時期に合わせて行われることが多いようです。
「打ち水」はもともと、神様の通り道を清めるために行われていたものが、江戸時代のころには涼を得るために行われるようになったそうですよ。

7月23日ごろ


8月8日ごろ
日中はまだまだ暑いですが、朝晩の風に少しずつ涼しさが混じってくる頃です。この時期は夕方にはひぐらしが鳴き始めます。
空を見上げると、積乱雲のような夏の代表格の雲が目立つ反面、秋を感じさせるようなうろこ雲などが見られることも。このような空を「行き合いの空」と呼びます。
この時期の言葉として、「山滴る」という言葉もあります。木々の緑が美しく、滴るように茂っている様子を表しています。
「処」という文字には落ち着くという意味があり、ようやく暑さがおさまり、朝晩に秋の気配が感じられる頃。日の長さも目に見えて短くなり、秋に近づいていることを実感できます。
穀物が実り始めますが、台風シーズンでもある時期。農家はまだまだ気が抜けません。風をおさめるためのお祭りも各地で行われます。
8月23.24日には地蔵盆という行事があります。お地蔵さまに日頃の感謝を伝える日として、町内のお地蔵様をおまつりし、子どもたちの健やかな成長を願います。

8月23日ごろ

9月8日ごろ
太陽が離れていくため、空が高くなり、本格的な秋を感じるころです。残暑が落ち着き、昼夜の気温差が大きくなることで朝夕に露が降りるようになります。春に日本にやってきたつばめも、さらに暖かい南の地域に飛び立つ頃。
大きな行事としては「中秋の名月」。これは旧暦8月15日の十五夜にお月見をするならわしです。旧暦8月15日はお芋の収穫時期でもあったため、無事に収穫ができた感謝の気持ちを込めてお芋をお供えする地域もあったことから「芋名月」とも呼ばれます。
太陽が真東から昇り、真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ等しい時期です。秋分を境に夜が長くなり、お月さまも美しいこのころには「秋の夜長」という言葉があります。
あちらこちらで見かける彼岸花は、地方によって呼ばれ方が異なり、呼び名は1000以上あるそうです!面白いものでは「きつねのちょうちん」。きつねが夜道を歩くとき、火をともす花だと言われているからだそう。思えば、ごんぎつねでも彼岸花の描写がでてきますね。

9月23日ごろ

10月8日ごろ
草などに冷たい露がおり、秋の長雨もひと段落。
朝晩の冷え込みも強くなります。このころから紅葉も色づき始め、日に日に秋が深まっていきます。秋の山が色濃く紅葉していく様子を「山粧う」と言います。春の「山笑う」夏の「山滴る」に続く、山の四季を表現する言葉です。
天気も良く、日中は過ごしやすい時期。燕のような夏鳥は南に移動し、雁などの冬鳥が日本にやってきます。
秋はますます深まり、朝晩の冷え込みが強くなってきて朝霜がみられるころです。ひとつ前の「寒露」では凍っていなかった露が、ついに凍るようになります。
木々の色づきも増してきますが、この色づきは朝晩の寒暖差によるものだそうで、目安としては朝の気温が10度を下回るようになると紅葉が始まるそうです。

10月24日ごろ


11月8日ごろ
冬の始まり。立春、立夏、立秋と並び、季節の大きな節目です。
この時期、寒い地域では「霜柱」が見られます。霜柱は地表に見られる氷の柱で、踏むとザクザクと音がする、冬の訪れを感じさせるもの。舗装された道が多くなった昨今ではなかなか見かけなくなりました。
この頃の雨を「時雨」といい、ひとあめごとに寒さが増して、一歩ずつ冬に近づいてゆきます。日差しは少しずつ弱くなり、木枯らしが吹きはじめ、寒さを感じるようになってきます。木枯らしはその字のとおり「木を枯らす」風、強く冷たい風です。
雪が降り始めるころという意味です。
この時期の言葉に、「木の葉時雨」という言葉があります。そもそも時雨という言葉は晩秋から初冬に降る断続的な雨のことですが、木の葉時雨は木の葉が散る様子を時雨にたとえたもののことだそう。
旧暦の10月にあたるこの時期は、気候や陽気が春に似ていることから、「小春」と呼ばれることもあったそうです。この時期の暖かな晴天の日を「小春日和」と呼ぶことともつながって、本格的な冬の前のひと時の陽気、と実感します。

11月22日ごろ
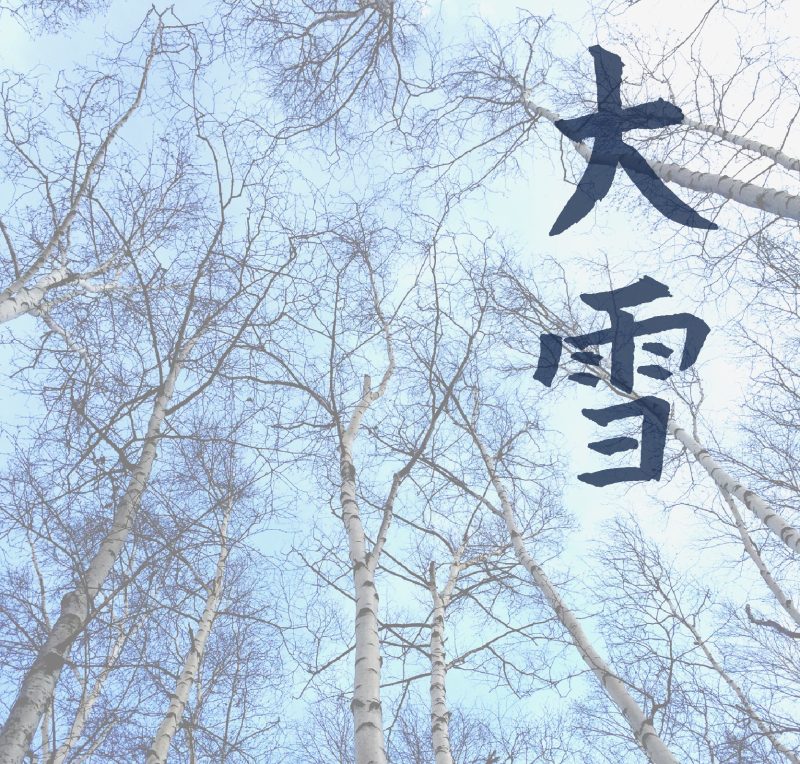
12月7日ごろ
「雪がたくさん降る時期」です。山肌は白くなり、本格的な冬の到来を感じるころで、寒さも強まってゆきます。毎年12月13日には「正月事始め」があります。正月を迎える準備をこのころから始める日、という日で、薪を調達したり、寺院ではわらですすを払ったりと、少しずつ準備を進めてきます。この「すすはらい」が大掃除のルーツだと言われています。
山の動物たちはそろそろ冬眠の時期。ここから2月の「啓蟄」のころまでは冬ごもり。冬至に向かって日照時間は短くなり、人間も含めて動物の活力は低下していく時期です。
一年で最も昼が短い時期で、ここを境にどんどん日が長くなります。
それを衰えていた太陽の力が勢いを増す「太陽の復活」と考え、「一陽来復」と呼び、「幸福に向かう」という意味もあります。
柚子は太陽を意味し、弱まっている太陽の気を補うものとされました。柚子湯につかり、柚子の香りで邪気をはらいます。また、かぼちゃ(なんきん)、「れんこん」「にんじん」など「ん」が2つつく食べ物は運がつくとされています。
これから迎える厳しい寒さを乗り切るための、先人の知恵がつまったならわしです。

12月22日ごろ

1月6日ごろ
「寒の入り」であり、小寒から節分までを「寒の内」とよびます。寒さが本格的に厳しくなり、冬本番です。
この時期の行事は「鏡開き」。1月11日に、年神さまにお供えした鏡餅を割り、雑煮などにしていただきます。日本人は言葉にも魂が宿り、言葉にしたものは現実になると考えてきました。そこで言葉を置き換えることで縁起の悪い言葉を避ける習慣から、「鏡割り」とは言わず、「鏡開き」と呼ばれます。
また、鏡餅は神聖なものなので、刃物で切るのではなく、木槌などで割るならわしがあります。
冬将軍が大暴れ!一年で最も寒い時期です。
寒さの底であるこの時期の早朝や夜間など、寒い時間帯に行う稽古を「寒稽古」といいます。芸事そのものに加え、この時期に行うことで寒さに負けないような精神力を鍛えるという意味もあります。
七十二候では「ふきのはなさく」。
早春の代表格「フキノトウ」が、雪の下から顔を出してきます。

1月20日ごろ